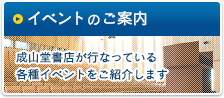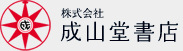コラム
2010年12月16日
著者へのインタビュー【吉田宏一郎さん】

専門分野を学ぶシニアの学生、修士課程の院生、研究機関や企業で働く若い研究者、技術者を主要読者対象と考えています。このような方々が、有限要素法や特異点分布法に関わる詳細な技法を学ばれる前に、本書により数値解析の基礎や必要な理由を認識されることが望ましいと思います。
海洋工学との出会い
昭和41年に大学院を出て暫くの間、船舶の部分構造の弾塑性解析法を研究していましたが、一方で、研究テーマに関し、我が国固有の必要性に基づく対象を、新しい技術を開発利用し、対象構造の全体構造を周辺の海洋環境を含め、総合的に扱いたいという強い願望を持っていました。その頃、新しい関西国際空港を大阪湾内に海上空港として建設する話がぼつぼつ話題になり始め、次第に具体的し、建設工法が大きなテマになりました。工法としては、海洋土木業界の押す埋め立てが有力でしたが、造船業界は半潜水式構造という、当時、まだ目新しかった浮体形式を採用した、大胆な工法を提案しようとして予備検討を始めていました。そのような流れの中で、私は、このテーマこそ自分の希望する条件を満たす研究テーマであると自覚し、昭和40年代半ば頃かと思いますが、思い切って、船舶工学から海洋工学へ移ることを決意しました。
当時の日本造船業界の雰囲気
昭和30年代は商船の大型化、建造法の革新も僅かずつでしたが、40年代に入る頃から、世界景気の影響を受け商船、特にタンカーの大型化が急速に進み、同時に建造法に関しても、溶接法が進歩し、またそれぞれの造船所が自社の事情に合ったブロック建造法、先行艤装工法などを開発して、建造量は大幅に増加し、造船ブームが到来しました。これは昭和50年頃まで継続しました。
昭和55年に関西国際空港工事(関空第1期工事)は埋め立て工法に建設が決まり、半潜水式構造を使用する造船業界の提案は、前例が無いという理由により採用になりませんでしたが、その前後より、海外における海底石油・天然ガス開発の活発化とともに、急激に生産あるいは掘削に用いられる海底支持式および浮遊式海洋プラットフオームの発注が増え、造船業界に海洋開発ブームが到来しました。
昭和55年に関西国際空港工事(関空第1期工事)は埋め立て工法に建設が決まり、半潜水式構造を使用する造船業界の提案は、前例が無いという理由により採用になりませんでしたが、その前後より、海外における海底石油・天然ガス開発の活発化とともに、急激に生産あるいは掘削に用いられる海底支持式および浮遊式海洋プラットフオームの発注が増え、造船業界に海洋開発ブームが到来しました。
研究者生活における一番の思い出
私は、海洋構造物の研究へ分野を移したばかりの頃、先ず手始めに水槽実験をやろうとしたのですが、すべてが始めてであって、皆目、見当がつきません。そこで、水槽実験の前に、自宅の台所の諸道具を利用して、例えばコラムにはアルミ缶を用いるなどして簡単な半潜水式構造体模型を作り、風呂桶に水を張り浮かべ、手で初期条件を変えて各種の固有モードを確認したりしました。このようにして大凡の感覚を掴んでから、大学の実験水槽をお借りし、模型にも計測装置を搭載あるいは貼付して定量的計測ができるようなものを何とかつくり上げ、曲がりなりにも浮体式構造体の水槽実験ができるようになりました。
一方、解析法の開発につきましても、似たようなプロセスがありますが、お話が長くなりますから省略します。結果として、浮遊式骨組構造を外殻要素と梁要素とに分け、それぞれに機能を分散させた解析モデルの、もっとも初期のものができました。このモデルによる解析結果と実験による計測結果とを比較しましたところ、例えば、梁の弾性変形による極めて小さい値、すなわち数マイクロ程度の大きさの値まで、両者の相関が良好であることを見いだした時には、ちょっと信じられず、何度もやり直すとともに、原因を考えてみました。その結果、空中の構造応答の実験におきましては模型の支持装置が必要であり、そこにおける境界条件が不明瞭になりやすく、小さな歪みは誤差範囲内に入ってしまい使えないわけですが、完全浮遊式の水槽実験においては支持装置はありませんから、小さな歪みもきっちり応答を表わしていることを理解し、相関が良好であることは解析法が信用できることであると悟ることができた時のことは、忘れることができません。
一方、解析法の開発につきましても、似たようなプロセスがありますが、お話が長くなりますから省略します。結果として、浮遊式骨組構造を外殻要素と梁要素とに分け、それぞれに機能を分散させた解析モデルの、もっとも初期のものができました。このモデルによる解析結果と実験による計測結果とを比較しましたところ、例えば、梁の弾性変形による極めて小さい値、すなわち数マイクロ程度の大きさの値まで、両者の相関が良好であることを見いだした時には、ちょっと信じられず、何度もやり直すとともに、原因を考えてみました。その結果、空中の構造応答の実験におきましては模型の支持装置が必要であり、そこにおける境界条件が不明瞭になりやすく、小さな歪みは誤差範囲内に入ってしまい使えないわけですが、完全浮遊式の水槽実験においては支持装置はありませんから、小さな歪みもきっちり応答を表わしていることを理解し、相関が良好であることは解析法が信用できることであると悟ることができた時のことは、忘れることができません。
学際的な研究活動の意義
1986年に、日本造船学会としてASME(米国機械学会)傘下のOMAE国際会議(海洋工学と極地工学に関する国際会議)を日本に招致し、第5回大会を東京において開催しました。この時の実行委員の一人としての経験から、海洋工学の推進には、海洋開発の後発国である日本においては、造船学会一学会だけでは全く対応できないことを悟りました。そこで、海洋の理学・工学・技術に関係する七つの学協会の方々と相談し、一緒に1988年に海洋工学連絡会を立ち上げました。
共通の関心事に関して、常に顔を合わせ、話し合って結果を出してゆくことが大切であり、そして機が熟したら独立した研究団体となり、学会を設立することを目標にしました。この会の特徴は個人を対象とせず、学協会を会員とし、連絡会の運営に責任を持つ、持たないは会員学会の意志により選択でき、小さな学協会も参加しやすくするとともに、委員長、庶務理事等の任期と責任を明確に定め、個人色を払拭した運営方法としました。
活動として、海洋工学パネルを年2回開催し、その時々の時宜に適ったテーマを選び、関係会員学会からスピーカーを出し、バラエテイに富んだ内容とするよう努力がなされました。また、講演時間よりも長い討論時間を設け、各講演に対し、他学会員が遠慮なく十分な質疑応答ができる場を設けることを励行した結果、これが、この海洋工学パネルの一つの特徴として評価されるようになりました。
1999年に、日本海洋工学会と名称を変え、現在、9つの海洋関連学協会(日本船舶海洋工学会、日本建築学会、海洋音響学会、海洋調査技術学会、土木学会、日本水産工学会、資源・素材学会、日本沿岸域学会、石油技術協会)の集合体となり、海洋工学パネルと日本船舶海洋工学会との協同開催の海洋工学シンポジウムを年1回づつ開催しています。また、NPO法人の資格取得の申請がなされているように聞いています。
共通の関心事に関して、常に顔を合わせ、話し合って結果を出してゆくことが大切であり、そして機が熟したら独立した研究団体となり、学会を設立することを目標にしました。この会の特徴は個人を対象とせず、学協会を会員とし、連絡会の運営に責任を持つ、持たないは会員学会の意志により選択でき、小さな学協会も参加しやすくするとともに、委員長、庶務理事等の任期と責任を明確に定め、個人色を払拭した運営方法としました。
活動として、海洋工学パネルを年2回開催し、その時々の時宜に適ったテーマを選び、関係会員学会からスピーカーを出し、バラエテイに富んだ内容とするよう努力がなされました。また、講演時間よりも長い討論時間を設け、各講演に対し、他学会員が遠慮なく十分な質疑応答ができる場を設けることを励行した結果、これが、この海洋工学パネルの一つの特徴として評価されるようになりました。
1999年に、日本海洋工学会と名称を変え、現在、9つの海洋関連学協会(日本船舶海洋工学会、日本建築学会、海洋音響学会、海洋調査技術学会、土木学会、日本水産工学会、資源・素材学会、日本沿岸域学会、石油技術協会)の集合体となり、海洋工学パネルと日本船舶海洋工学会との協同開催の海洋工学シンポジウムを年1回づつ開催しています。また、NPO法人の資格取得の申請がなされているように聞いています。
日本における海洋工学研究者と産業界との関わり
従来は、通常の学会活動を通しての関係が主たる関わりであり、特別な目標を掲げた大規模なプロジェクトが組まれ、組織的な研究開発の遂行が必要な場合には、一定期間、纏まった額の研究費が保証され、大学研究者、国立研究機関研究者と企業関係者との協同作業が出来るような組織が作られて来ました。 2007年に海洋基本法が制定され、それを基礎に2008年に海洋基本計画が策定されて以後は、国家的規模の、中/長期間に渡たる実施計画に沿った研究開発が実行されることが始まったと考えますが、まだ新しい研究開発システムがしっかりと定着したわけではなく、今後の動向を注視してゆく必要があると思います。 一方、大学研究者の側によって、例えば、東京大学を中心として組織されている海洋技術フオーラムのように、企業の協力を得ながら、官庁とは一線を画して、日常的に検討を重ね、時に応じて国に対して提言等を行い、国の施策に影響を与えようとする動きも現れてきています。
最近の海洋を巡る政治・経済・社会問題と海洋工学・技術との関係
現在、世界的に見て、海洋工学・技術と最も深い関係を有する経済対象は、海底の原油・天然ガスを対象とする海底資源開発です。中東、北海、メキシコ湾、西アフリカ沖海域、リオデジャネイロ沖等において大規模な油田・ガス田が発見され、開発が進められてきました。しかし、これらの開発には、時に大きな問題が付きまといます。
例えば、2005年に、メキシコ湾を超大型のハリケーン・カトリーナとリタが相前後して襲い、稼動していた多数の掘削装置や生産装置が、風、波、流れによって破壊され、これらの設計基準の大幅な見直しの必要性が議論されています。この時はハリケーンの襲来は予想されていたことですから、予め各種の弁は閉められ、作業員も避難しましたから、主に、それらを支持する構造体であるプラットフオームに大きな被害が発生しましたが、人命喪失や大きな環境汚染は発生しませんでした。一方、本年4月から7月に掛けて、メキシコ湾における掘削中の油井において、暴噴に続いて大爆発が発生し、多数の死傷者が出るとともに無慮80万バーレルに及ぶ原油が噴出し、ルイジアナ州沖を中心に深刻な海洋汚染を引き起こしました。現在、原因究明と賠償責任が大きな問題となっています。これまでの、原油による海洋汚染の最大事故と言われるアラスカ湾におきます油タンカー(エクソンバルデイーズ号)の座礁事故に伴う漏出油4万バーレルの20倍と言う真に大きな事故であったわけです。
残念ながら、日本列島周辺海域には、大規模な油田・ガス田は賦存しません。しかし、現在、隣国中国との間で大きな政治問題になっています、東シナ海には天然ガスを中心として、相当量の海底資源が賦存し、政治的に折り合いがつけば、協同開発の可能性があると言われています。一方、我が国の排他的経済水域内に相当量の賦存があると言われ、先述の海洋基本計画などに基づいて、組織的な埋蔵量調査等が始まっている対象に、海底熱水鉱床やメタンハイドレート等があります。現状では、これらの新しい海底資源の開発に必要な技術が十分揃っているわけではなく、開発法そのものの開発とともに、それを構成する、必要な個別技術を同時にバランスよく開発してゆくことが重要になると思います。
例えば、2005年に、メキシコ湾を超大型のハリケーン・カトリーナとリタが相前後して襲い、稼動していた多数の掘削装置や生産装置が、風、波、流れによって破壊され、これらの設計基準の大幅な見直しの必要性が議論されています。この時はハリケーンの襲来は予想されていたことですから、予め各種の弁は閉められ、作業員も避難しましたから、主に、それらを支持する構造体であるプラットフオームに大きな被害が発生しましたが、人命喪失や大きな環境汚染は発生しませんでした。一方、本年4月から7月に掛けて、メキシコ湾における掘削中の油井において、暴噴に続いて大爆発が発生し、多数の死傷者が出るとともに無慮80万バーレルに及ぶ原油が噴出し、ルイジアナ州沖を中心に深刻な海洋汚染を引き起こしました。現在、原因究明と賠償責任が大きな問題となっています。これまでの、原油による海洋汚染の最大事故と言われるアラスカ湾におきます油タンカー(エクソンバルデイーズ号)の座礁事故に伴う漏出油4万バーレルの20倍と言う真に大きな事故であったわけです。
残念ながら、日本列島周辺海域には、大規模な油田・ガス田は賦存しません。しかし、現在、隣国中国との間で大きな政治問題になっています、東シナ海には天然ガスを中心として、相当量の海底資源が賦存し、政治的に折り合いがつけば、協同開発の可能性があると言われています。一方、我が国の排他的経済水域内に相当量の賦存があると言われ、先述の海洋基本計画などに基づいて、組織的な埋蔵量調査等が始まっている対象に、海底熱水鉱床やメタンハイドレート等があります。現状では、これらの新しい海底資源の開発に必要な技術が十分揃っているわけではなく、開発法そのものの開発とともに、それを構成する、必要な個別技術を同時にバランスよく開発してゆくことが重要になると思います。
「海洋構造力学の基礎」出版の動機
本書を執筆しました動機としては、まとめますと三つほどになります。
1.初学者が参考にし易い、日本語の海洋構造物の構造力学に関する書物が存在しないことです。
2.初学者に対して、デイジタル解析の基礎として、またデイジタル解析を補完するものとして、海洋構造力学に関するアナログ解析の考え方の理解の必要性を感じているからです。
3.上記に比較しますと、テーマとしてのスケールは小さくなりますが、 東大の旧吉田研究室における大型半潜水式構造物の波浪応答解析法の開発の流れを明らかにしておきたいことです。
先ず、1番目につきましては、私が適当かどうか、判りませんが、海洋構造物全般にわたる初学者向けの日本語の書物が存在しないことから、この本の原稿を執筆し、成山堂さんにご相談したところ、出版して下さることになったわけです。
2番目は、デイジタル解析法とアナログ解析法との関係についてですが、先ず、流体力学、構造力学は対象を連続体と仮定していますから、流体力学、構造力学のデイジタル解析の基礎はアナログ解析にあるわけで、アナログ解析の知識は重要であるわけです。次に、有限要素法に代表される、デイジタル解析技術はアナリシス技術としては極めて有力ですが、解析モデルの作成、出力結果に関する見通し、パラメタの効果の見通しなどシンセシスに関するテーマにつきまして直接的な解を与えてくれません。逆に、あまりに膨大な出力データが見通しのよい推測の邪魔をする弊害すらあると思います。アナログ解析法に関する知識はこのようなデイジタル解析の弱点を補完する手段として必要であると考えられます。加えて、アナログ解析の知識は構造工学の川上部分である構造基本計画に おいても有効であると思います。すなわち、構造基本計画のように、白紙にコンセプトを描き、その成立可能性を定量的に検討することは、当然ながらアナリシスではなく、シンセシスに属する手続きであり、このためにアナログ解析の知識が役立つと考えられます。
3番目につきましては、東大、東海大時代の旧吉田研究室におきます研究分野を大別しますと、構造継手強度のような純粋な構造強度の分野、大型浮体式構造物の波浪応答解析の分野、海洋構造物の位置・姿勢などの構造制御分野、浮体式構造物を核とする海洋空間利用計画の4分野となります。これらのうち、個別テーマとして最も息長く取り扱われ、関係論文が多いテーマが二つ目の大型浮体式構造物の波浪応答解析です。そこで、本書では、他のテーマは基礎のなかに埋め込み、このテーマを海洋構造物の動的応答解析の中心に配置してあります。因みに、本書のカバーに印刷されていますテンションレグ・プラットフオームは四つ目の海洋空間利用計画分野の成果の一例です。海洋底から立ち上がった海山の頂上に重力式基礎を置き、各種の海洋環境の調査、観測を行うとともに、有人潜水艇の海底基地となる複合プラットフオームであり、海上部と海底部とはエレベータで繋がれています。
1.初学者が参考にし易い、日本語の海洋構造物の構造力学に関する書物が存在しないことです。
2.初学者に対して、デイジタル解析の基礎として、またデイジタル解析を補完するものとして、海洋構造力学に関するアナログ解析の考え方の理解の必要性を感じているからです。
3.上記に比較しますと、テーマとしてのスケールは小さくなりますが、 東大の旧吉田研究室における大型半潜水式構造物の波浪応答解析法の開発の流れを明らかにしておきたいことです。
先ず、1番目につきましては、私が適当かどうか、判りませんが、海洋構造物全般にわたる初学者向けの日本語の書物が存在しないことから、この本の原稿を執筆し、成山堂さんにご相談したところ、出版して下さることになったわけです。
2番目は、デイジタル解析法とアナログ解析法との関係についてですが、先ず、流体力学、構造力学は対象を連続体と仮定していますから、流体力学、構造力学のデイジタル解析の基礎はアナログ解析にあるわけで、アナログ解析の知識は重要であるわけです。次に、有限要素法に代表される、デイジタル解析技術はアナリシス技術としては極めて有力ですが、解析モデルの作成、出力結果に関する見通し、パラメタの効果の見通しなどシンセシスに関するテーマにつきまして直接的な解を与えてくれません。逆に、あまりに膨大な出力データが見通しのよい推測の邪魔をする弊害すらあると思います。アナログ解析法に関する知識はこのようなデイジタル解析の弱点を補完する手段として必要であると考えられます。加えて、アナログ解析の知識は構造工学の川上部分である構造基本計画に おいても有効であると思います。すなわち、構造基本計画のように、白紙にコンセプトを描き、その成立可能性を定量的に検討することは、当然ながらアナリシスではなく、シンセシスに属する手続きであり、このためにアナログ解析の知識が役立つと考えられます。
3番目につきましては、東大、東海大時代の旧吉田研究室におきます研究分野を大別しますと、構造継手強度のような純粋な構造強度の分野、大型浮体式構造物の波浪応答解析の分野、海洋構造物の位置・姿勢などの構造制御分野、浮体式構造物を核とする海洋空間利用計画の4分野となります。これらのうち、個別テーマとして最も息長く取り扱われ、関係論文が多いテーマが二つ目の大型浮体式構造物の波浪応答解析です。そこで、本書では、他のテーマは基礎のなかに埋め込み、このテーマを海洋構造物の動的応答解析の中心に配置してあります。因みに、本書のカバーに印刷されていますテンションレグ・プラットフオームは四つ目の海洋空間利用計画分野の成果の一例です。海洋底から立ち上がった海山の頂上に重力式基礎を置き、各種の海洋環境の調査、観測を行うとともに、有人潜水艇の海底基地となる複合プラットフオームであり、海上部と海底部とはエレベータで繋がれています。
本書執筆にあたって特に気をつけたこと
専門分野を学ぶシニアの学生、修士課程の院生、研究機関や企業で働く若い研究者、技術者を主要読者対象と考えています。これらの方々に、先述のデイジタル解析とアナログ解析との関係を理解して頂く、特に、アナログ解析における基本仮定の基礎の上にデイジタル解析も成立していることを理解して頂くように説明に注意しました。
本書は構造力学の解説書ですから、構造設計につきましては、要所々において、解析技術を設計に応用する場合の考え方に言及していますが、系統的な説明は与えられていません。ただし、最後の8章におきまして、構造の安全設計の設計基準となる、代表的な破壊、破損現象について、設計基準としての最も原理的な使い方を解説し、構造設計へ繋ぐ橋の役を期待しています。
海洋構造物の全体構造としての動揺振動現象の解説において、主要な柱になっている考え方は、大型半潜水式構造物を、弾性体として構造力学の対象と見なす場合には3次元骨組構造、波浪荷重の評価のため流体力学の対象と見なす場合には分割剛体要素の集合と見なすものとして、これら二つのモデルを合体し、点と線に集約して線形システムとする方法です。この考え方と具体的成果としてのソフトウエアは、東大の旧吉田研究室の成果であり、今後、現実問題において、さらに広く使用されることが期待される一方、本書に記されている、解法の有する特性についても認識されることが望ましいと考えています。
また、最近の海洋システムの設計においては、信頼性理論に基づく設計法が重要な位置を占めるようになって来ていますので、自然環境に関わる荷重の評価の一部に、そのような考え方を取り入れて説明してあります。
本書は構造力学の解説書ですから、構造設計につきましては、要所々において、解析技術を設計に応用する場合の考え方に言及していますが、系統的な説明は与えられていません。ただし、最後の8章におきまして、構造の安全設計の設計基準となる、代表的な破壊、破損現象について、設計基準としての最も原理的な使い方を解説し、構造設計へ繋ぐ橋の役を期待しています。
海洋構造物の全体構造としての動揺振動現象の解説において、主要な柱になっている考え方は、大型半潜水式構造物を、弾性体として構造力学の対象と見なす場合には3次元骨組構造、波浪荷重の評価のため流体力学の対象と見なす場合には分割剛体要素の集合と見なすものとして、これら二つのモデルを合体し、点と線に集約して線形システムとする方法です。この考え方と具体的成果としてのソフトウエアは、東大の旧吉田研究室の成果であり、今後、現実問題において、さらに広く使用されることが期待される一方、本書に記されている、解法の有する特性についても認識されることが望ましいと考えています。
また、最近の海洋システムの設計においては、信頼性理論に基づく設計法が重要な位置を占めるようになって来ていますので、自然環境に関わる荷重の評価の一部に、そのような考え方を取り入れて説明してあります。