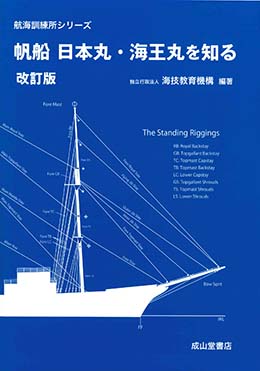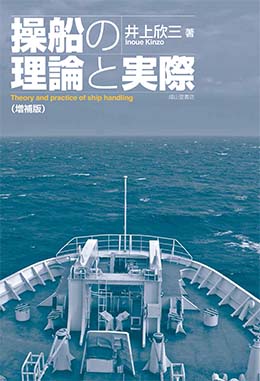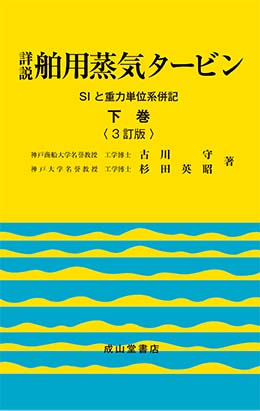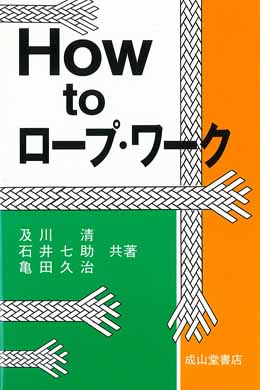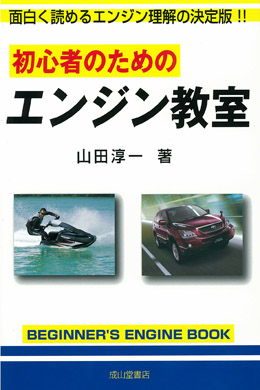海事の書籍紹介
航海訓練所シリーズ 帆船 日本丸・海王丸を知る(改訂版)
独立行政法人 海技教育機構 編
世界最大級の帆船、日本丸と海王丸の仕組みと運航技術を1冊に収録。マスト、帆、ロープの詳細な図解で複雑に見える帆船の構造を理解できる。帆走理論、航法などの専門知識を現役の航海士が丁寧に解説。
【はじめに】より
本書の基になった帆船操典の作成は昭和37年にまで遡ります。当時の日本丸船長であった千葉宗雄教授が主として執筆された原稿をもとに帆船操典の初版を発行し、その後「高所及び帆船作業指針」(昭和38年3月)、「帆船操典(追録)」(昭和41年3月)を加え、昭和42年2月、実習上の便宜を図るため本文と付図の2分冊として発行しました。昭……
舶用電気・情報基礎論−航海計測・機関計測の基礎知識−
若林 伸和 著
舶用計測に関わる電気工学、無線通信、コンピュータ利用の基礎技術を解説。航海科、機関科学生や電装関連の造船技術者等に必携の1冊。
著者からこの本を読まれる方へ(「はじめに」より)
20世紀(1901年?2000年)は、人類史上でも飛躍的にテクノロジーが進歩した100年であったといえるでしょう。電気が利用されるようになり、電子技術が開発され、20世紀中頃にはコンピュータが発明されて情報技術が発展しました。今日の社会においてはこれら電気・電子・情報そして通信技術を基盤とした様々なシステムによるサービスを利用して生活しています。
……
操船の理論と実際(増補版)
井上 欣三 著
船舶の安全運航に必要な操船の理論と、実際の船の動きを結び付け体系化。近年の船型の多様化と大型化に対応した新しい操船の教科書。
★本書のポイント★
●船舶の安全運航に必要な、操船の「理論」と「実際」を結び付け体系化。
●操船に関する科学的知識を踏まえ、海上で
「実際に船はどう動くのか」を実務的観点から詳細に解説。
●近年の船型の多様化と大型化に対応した新時代の操船の教科書。
●現場で有用な各種船舶の操船性能をデータベース化。
シミュレーションでの研修にも役立つ。
【『操船の理論と実際』増補版発刊にあたって】……
ブリッジ・リソース・マネジメント
廣澤 明 訳
船舶の安全運航に有効なブリッジ・リソース・マネジメントの原則を解説。タイタニック、エクソン・バルデスなど、過去の海難事例を分析し、人間が犯すミスの要因を探り、事故防止に役立てる。
詳説 舶用蒸気タービン【下巻】(3訂版)−SIと重力単位系併記−
古川 守・杉田英昭 共著
蒸気タービン及び付属装置の構造、運転、保守、開放及び検査等について詳細に解説。LNG船用蒸気タービンプラントの章と演習問題を追加した改訂版。
【3訂版発行に当たって】
本書が1984年(昭和59年)に発行されて今年で35年, 2訂版が2009年(平成21年)に発行されてからも10年になります。最初に本書改訂版が発行された2002年(平成14年)は,舶用蒸気タービンがLNG タンクから漏れ出すボイル・オフ・ガスBOGを有効活用でき,またそれを有効に処理できる最も適した主機関として,LNG船に独占的に採用されていた時代でした。
……
四・五・六級 航海読本(2訂版)
及川 実 著
過去に出題された海技国家試験を徹底分析。出題傾向に沿って重点解説。法令改正に伴い、内容を改めた改訂版。
【まえがき】より
船舶職員(船長や航海士など)を志す方々にとって,海技士の免許の取得は必須であり,そのためには海技士国家試験(以下「海技試験」という。)に合格しなければなりません。
海技試験の勉強をするうえで先ず把握しておかなければならないのが,学科試験の試験科目と試験の出題範囲です。海技士(航海)の資格における試験科目には「航海に関する科目」,「運用に関する科目」,「法規に関する科目」及び「英語に関する科目(六級海技士……
六訂版 航海学 【上巻】
辻 稔・航海学研究会 共著
水路図誌、航程線航法、大圏航法、潮汐潮流などの地文航法とGPS、レーダなどの電波航法を解説。計算器を使った例題付。海技士(航海)1〜3級向。
【はしがき】より
航海学の専門図書としては多数の名著が出版されていますが、学生の能力に応じた適当な教材または参考書の発刊を望む声も少なくありません。
このような要望にこたえて本書が発刊されて以来20数年の年月が過ぎました。
この間、航海学の分野においても科学技術の進歩に伴い、各種電波計器の自動化、船位表示のデジタル化、自動衝突予防装置の開発、NNSS、GPSの普及等目覚ましいものがあ……
How to ロープ・ワーク
及川 清・石井七助・亀田久治 共著
基本的なロープの結び方、これを応用した各種の実用的な結び方・装飾的な結び方をイラストを中心にやさしく解説。万人向きの結びの本。
【まえがき】より
わたくしの家業の関係からか、小学生のころからロープを手にするようになったが、当時は、“よぼい”や“さつま”と読んでいた“垣根結び”や“ショート・スプライス”、あるいは“もやいむすび”などができる程度であった。
ところが戦時中の中学校の動員先が航空機の格納庫用天幕や爆弾用の落下さんの製作工場であったため、ここでもロープ・ワークやキャンバス・ワークをいや応なしに体得させられた。そして、……
初心者のためのエンジン教室
山田淳一 著
誰もが頭を悩ますエンジンの仕組や動きを、多くの図を用い易しくわかりやすく説明。苦手意識克服に役立つ。水上バイク愛好家にもお薦め。
【まえがき】より
エンジンがわからないと悩んでいる初心者のための、この本を書きました。
エンジンを知らなくて損をしている人のためにこの本を書きました。
ガソリンが燃えるとなぜ車が走るのか?
ディーゼルエンジンはなぜ燃料消費量が少ないのか?
エンジンオイルはなぜ交換しなければならないのか?
冬になると車の排気管から水滴が落ちるのはなぜか?
下り坂で車のエンジンブレーキがかかるのは……
五訂版 航海学 【下巻】
辻 稔 著
天文概説から船位の決定に至る天文航法のすべてを理論と実際面から体系的に解説。海技試験問題例も多数収録しテキストに最適。1〜3級向。
【五訂版発行にあたって】
近年の航海学の進歩はめまぐるしく、天文航海学の分野においても同様です。かつて、天測による船位の算出は航海士にとって必携の技術でしたが、GPS等の普及により実務では六分儀を持つ機会も少なくなってきています。しかし、海技士を目指す人たちにとってその学習は必要不可欠なものであり、避けて通ることはできません。今回の改訂では、例題に卓上計算機での計算方法を具体的に示しました。また……