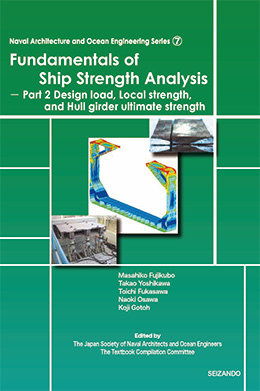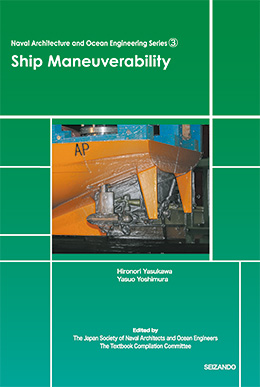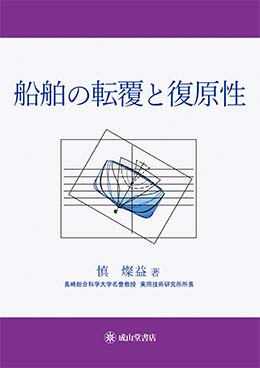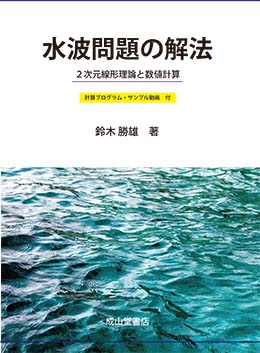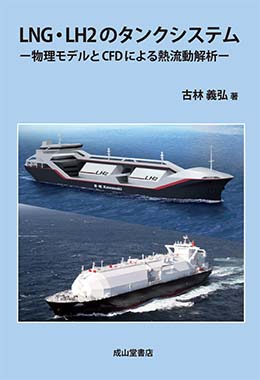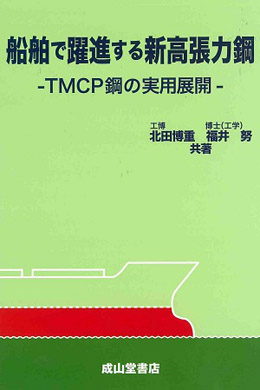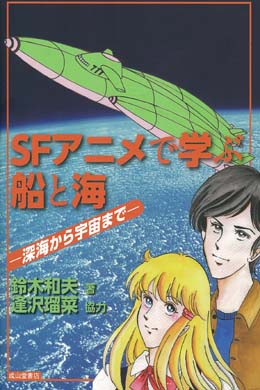海事の書籍紹介
Ship Production System
Fundamentals of Ship Strength Analysis – Part2 Design load, Local strength, and Hull girder ultimate strength
Ship Maneuverability
Resistance and Propulsion
Ship Geometry and Fundamentals of Hydrostatics
Yoshiho Ikeda・Yoshitaka Furukawa・Toru Katayama・Tokihiro Katsui・Motohiko Murai・Satoru Yamaguchi
船舶の転覆と復原性
慎 燦益 著
本書は、「船の復原性」についてはこれまでの普遍的な内容をできるだけ「船の転覆」と結び付けて、「船の安定性・安全性」を確保する観点からまとめており、「船の転覆」については「船の復原性」に関する説明文の行間から読み取るのではなく、できるだけ直接的に言及・記述しています。
【はしがき】
「船の転覆」を防ぎ、人と船の安全性を確保することは、造船学上の最も重要な問題の一つである。
船は水上に浮かぶ構造物のひとつであるから、構造物としての横安定性だけを考えれば、造船学上はすでに一定の成果をもたらしていると言っても過言ではない。
にも拘……
水波問題の解法 ー2次元線形理論と数値計算ー
鈴木勝雄 著
重力の作用によって、水面に生ずる重力波―水波。
この水波の中に、静止したり、揺れ動いたり、進行したりする物体があるときに、その物体の周りに波がどのように生じ、変形するのか。物体には、どのような力が働き、どのように揺れるのか。
コンピューターの発展により、純数値計算が容易になった現在、あらためて古典的な計算方法を用いた解法を学び、その意義を問い直す。
計算プログラム・サンプル動画 付
【計算プログラム・サンプル動画】は以下からダウンロードしてください。
【計算プログラム】
■低常造波問題
SemiSubCircle……
LNG・LH2のタンクシステムー物理モデルとCFDによる熱流動解析ー
古林義弘 著
長年の研究成果を基に、4つのタンク様式ごとに支配力方程式を作成。
実務者に必要な固有の解を得るために、多くの条件設定をして数値解を算出。
超低温液化ガスの熱的な挙動や電熱現象を解説した稀有な一冊である。
【まえがき】より
最近のクリーンエネルギーとしての世界的なLNG海上輸送の増加や各種のタンク方式の開発と実用化を眺めると、著者が最初にLNG関連の研究、設計を始めた1970年当時から考えると隔世の感がある。また次世代エネルギーとして注目を浴びるようになった水素エネルギーの現状、さらに家庭向けの燃料電池の普及や一般消費者向けの燃料電池……
船舶で躍進する新高張力鋼―TMCP鋼の実用展開―
北田博重・福井 努 共著
日本の造船界、学会、船級協会ほかが技術を結集して開発してきたTMCP鋼と呼ばれる高性能の鋼材について、
安全性確保の検討・評価を船級規則からの視点でまとめた一冊!船会社、造船所、製鉄所、船級協会の若手技
術者や船舶の設計、施工、材料の開発実務者の方にオススメです。
【まえがき】より
日本の造船業は、高度成長期の1960年代中頃には新造船の建造量で全ヨーロッパを抜き、世界の建造量の約50%を占めるまでに成長した。その後2度の造船不況に見舞われたが、1990年以降のグローバルな経済発展に伴う船舶需要拡大により日本の建造量は右……
SFアニメで学ぶ船と海−深海から宇宙まで−
鈴木和夫 著・逢沢瑠菜 協力
航空宇宙工学やロボット工学関係者は、SF作品やアニメ、コミックに影響を受けてその専門の道に進んだ人が多い。本書は、そのような人材を船舶海洋工学の分野でも増やしたいという著者の願いを実現したものです。船や海に関するSF作品やアニメを取り上げて、実際の物理学的な現象と対比しながら船舶海洋工学(流体力学)の話を進めています。あくまで工学的な内容を中心としていて、SF作品は導入として用いているだけで、科学的な検証をしているものではありません。
【はしがき】より
本書では、主に船や海が登場するSF作品(コミック、アニメ、小説、映画)あ……