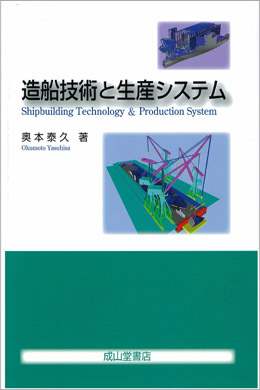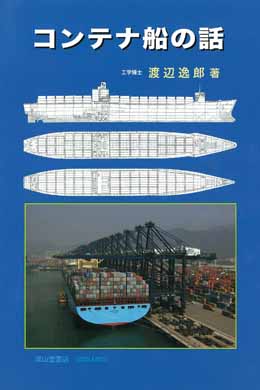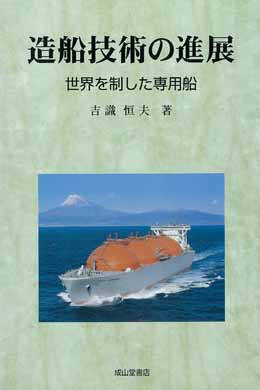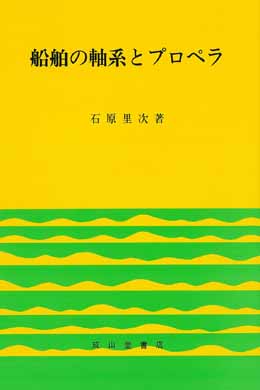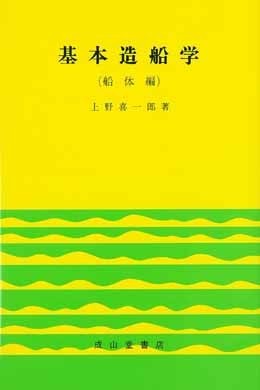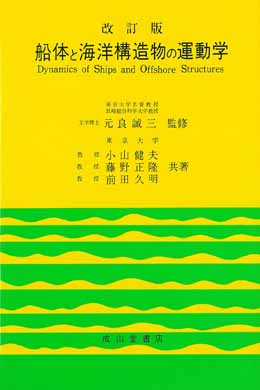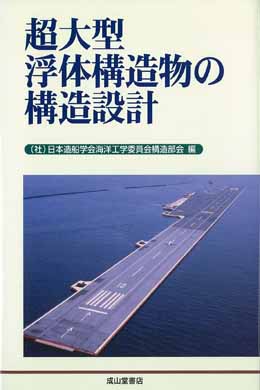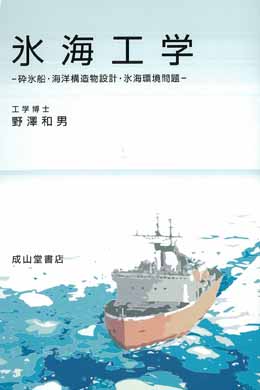海事の書籍紹介
商船設計の基礎知識【改訂版】
造船テキスト研究会 著
基本用語から法規にいたる概要、基本計画、船殻・船体艤装設計について、設計の実務者がわかりやすくまとめた入門書。
【まえがき】より
本書は昭和59年9月に初版を出版し、また平成7年に改訂した「商船設計の概要」の全面改訂版である。改訂に当たっては、新しい技術の進歩や関連する規則を取り入れて見直しを行ったほか、一層分かりやすい記述や各編の整合性にも充分な配慮を心掛けた。また書名もこの機会に「商船設計の基礎知識」に改めることにした。
本書の意図するところは、これから商船の設計を勉強しようと思っておられる学生や技術者に、実……
造船技術と生産システム
奥本泰久 著
幅広い造船技術を生産システムの面からとらえ、建造技術の発達の歴史や、現在の最新技術を紹介した本。
造船業界は長引いた不況の影響で、団塊の世代である造船のベテラン技術者・技能者が退職した後の後継者が育っておらず、技術や技能の継承に断絶が見られています。
著者は大阪大学接合科学研究所特任教授。企業で技術開発やシステム開発に携わった経験と、その後の大学での研究成果を合わせ、その蓄積を次世代に残そうと本書をまとめました。
造船システムの歴史と概要、生産計画・管理、3次元CADを中心とした生産設計、切断・曲げ・溶接・艤装・塗装など各工事の基礎と……
コンテナ船の話
渡辺逸郎 著
今から40年ほど前、初めて海上コンテナ輸送が開始されたときは、海運に一大変革をもたらすものとして、驚きと期待をもって迎えられたことを記憶している方も少なくないでしょう。今日ではこの輸送システムはすっかり定着し、コンテナ船も初期の数百個積みから今や1万個積みにまで大型化してきています。ここに至るまでにはさまざまな輸送方式の船が登場しましたが、主流はほぼ一貫してセル構造のフルコンテナ船でした。
本書は、このコンテナ専用船に的を絞って、発展の系譜をたどったものです。
コンテナ輸送開始の頃からしばらくの間は関連書籍も数多く出版されましたが、最……
造船技術の進展−世界を制した専用船−
吉識恒夫 著
わが国造船業は、1956年に建造量世界一を達成して以来、約半世紀にわたって世界をリードし、現在もトップグループを維持し続けています。このように日本が長期間にわたり世界を牽引する立場にある大規模産業は非常に稀です。景気変動・新興国の台頭などを経て未曾有の船舶建造ラッシュに沸く昨今、日本における海事産業の重要性が再認識されつつあります。そのような折、わが国造船技術の発展過程を豊富な事例で解説した書籍を発行しました。
本書は,幕末維新期から現在まで、わが国が造船大国として成長・成熟していく過程を時系列であらわす一方、ポイントとなる新技術の開……
船舶の軸系とプロペラ
石原里次 著
推進軸系とプロペラの保守・管理の実際を豊富な図面をもとに実務者、海技試験受験者向に解説。新しい推進技術も紹介する。
【まえがき】より
長年、練習船の機関士として、また、海難審判庁の審判官、理事官としての職務についてまいりました。この間に多くの先輩から貴重な指導を受け、また、実務にあたり、必要に応じていろいろな資料、参考書を集めてきました。今回、退職したのに伴い、これらの資料をこのまま散逸するのも惜しいとの思いから系統的に整理し、軸系装置についてまとめてみました。
モーターボートから大型船までの装置を対象にし、現在では実用……
金属材料の腐食と防食の基礎
世利修美 著
金属の腐食解明と防食対策に取り組む際に必要な概念や用語等の基礎知識を数式もまじえて、丁寧にわかりやすく解説した入門書。
【序文】より
本書は「腐食はどうもわからん!」と思っている方のために書かれた本である。特に、材料学や化学が得意でない技術者のために書かれたものである。
著者自身、企業の技術者として腐食防食の問題に直面し、困って独学した経験がある。アノードとカソード、陽極と陰極、正極と負極、電位と電極電位・・・等の専門用語に悩まされ、『電位の低い電極から高い電極へ腐食電流は流れる』と言った記述に「逆ではないのか?」と混乱した経験……
基本造船学 【船体編】
上野喜一郎 著
鋼船についての基礎に始まり、船体の構成、鋼船の材料、鋼材の接合、船体の一般構造、特殊船体構造まで、図表を豊富に使って解説。
【序】より
船に関係のある仕事に就いて30余年、その間、本職(逓信省管船局→運輸省船舶局)のほかに、縁があって東京高等商船学校で10年間、工学院で2年間、東京明治工業専門学校で5年間、丁度戦前から戦後へかけて、10数年間、造船学特に鋼船の構造について講義をしたことがある。
当時、それらの講義には、教科書を使用せず、自分で作った講義の原稿に基づいていた。いざ教えるとなると、いろいろと疑問が起こって更に……
【改訂版】 船体と海洋構造物の運動学
元良誠三 監修 小山健夫・藤野正隆・前田久明 共著
船舶及び海洋構造物の運動を、基本から解説したもので、船舶工学、海洋工学をはじめてまなぶ学部学生や操船に携わる実務者などの参考書。
【目次】
船体運動に関する学問は、昭和30年代から急速に発展し、ついで石油掘削リグなどの浮遊構造物が盛んに建造されるにしたがって、浮遊海洋構造物の運動や係留に関する研究が、活発に行なわれるようになってきた。
ところが、この分野における専門書は極めて少なく、教科書または参考書になるような専門書にたいする要望は、かねてから強かった。
本書は研究成果も織り込み、また記述の正確を期してあるので、専門の方々の参考書……
超大型浮体構造物の構造設計
(社)日本造船学会海洋工学委員会構造部会 編
超大型浮体構造物(メガフロート)は、全長5?におよぶ海上に浮かぶ大地であり、空港・物流基地・海洋観測基地・発電所等への利用が期待されています。従来の埋立て工法に比べて自然への影響が小さく、工期・耐震性・汎用性などにも優れた点が多いといわれ、平成7年からメガフロート国家プロジェクトがスタートしました。これを契機として構造設計技術は長足の進歩を遂げ、特に流力弾性応答、係留設計、安全性評価などのコア技術について多くの研究成果が得られました。
本書は、超大型浮体構造物を設計する上で核となるこれらの技術を造船初学者にもわかるように平易に解説し……
氷海工学−砕氷船・海洋構造物設計・氷海環境問題−
野澤和男 著
海氷の性状を基本に、流体・構造・材料・破壊・熱などの各力学、極地の環境、砕氷船、リグ等、北極圏の開発に必要となる工学を纏めた内容。
【まえがき】より
1973年10月に勃発した第4次中東戦争が原因となった石油価格の大幅な引き上げは第1次オイルショックを起こし、さらに第2次オイルショック(1978年)へと発展した。この出来事は世界の経済界に大きな打撃を与えた。特に、中東に石油エネルギーの大部分を依存する日本では安定供給を揺るがす重大問題となった。一方、Canada、Alaskaの北極圏では、North Slopeの石油発見(19……