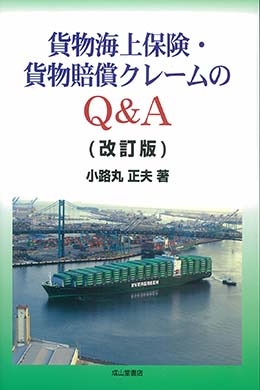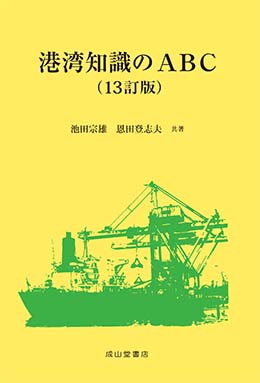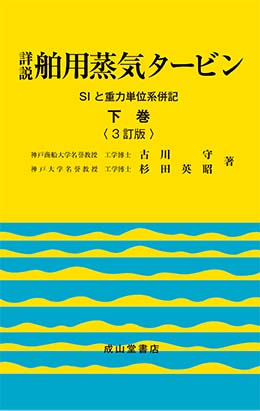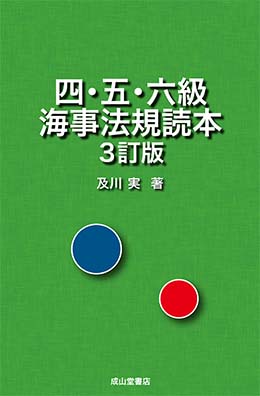海事の書籍紹介
貨物海上保険・貨物賠償クレームのQ&A(改訂版)
小路丸正夫 著
貨物保険・貨物賠償クレームの実務は、貿易・海運・NVOCC・損保・PIの損害調査・海事法務の担当者、および商社・メーカーの保険担当者の重要な仕事のひとつです。しかしながら、法理論・実務とも精通しなければ対応が難しいとされ、実例をふまえたわかりやすい解説書が求められていました。
本書は、クレーム対応実務の肝を網羅的に整理し、単なるマニュアルではなく、実例から理論を構築して応用力が身につくよう解説しています。2009年に大きく改訂された協会貨物約款(ICC)と旧約款の違いと特徴も随所で触れるなど、最新事情にも対応しています。また、ク……
港湾知識のABC【13訂版】
池田宗雄・恩田登志夫 共著
港湾の形態・分類、船舶との関係、貨物・荷役関連、各種施設、法令、港湾計画・工事等について概説。港湾関係業務に携わる人の入門書。
◆こんな方にオススメです!
港湾や埠頭に勤めている人、港湾関係の行政に携わっている方。
[toc]
【初版はしがき】
わが国の海岸線の形状は複雑で変化に富み、ずばらしい美しさで、多くの国立公園や国定公園が指定されています。海は岸のすぐ近くまで適当な水深があり、岬や島が風や波を遮る湾や入江が多く、わが国ほど至る所に港の所在する国は世界でも例を見ません。
しかし、自然条件は厳しく、年間多数の……
内航船員用 海洋汚染等・海上災害防止の手びき−未来に残そう美しい海−
(社)日本海難防止協会海洋汚染等・海上災害防止研究会 編著/日本内航海運組合総連合会 発行
海洋汚染防止法に基づく規制や事故発生時の対応をまとめたもの。実務的な運用方法をカラーで解説。
◆こんな方にオススメです!◆
内航船員、廃油処理業者、油防除機材販売会社
【はじめに】より
内航海運は長距離・大量輸送に適した輸送手段として、国内貨物輸送量全体の40%(トン・キロベース)以上のシェアを担ってきた。内航海運は輸送に必要なエネルギーがトン・キロベースで自家用トラックの約18分の1、営業用トラックの約5分の1、さらに二酸化炭素の排出量が自家用トラックの約60分の1と言われ、省エネ効果に優れ、環境にもやさしい輸……
詳説 舶用蒸気タービン【下巻】(3訂版)−SIと重力単位系併記−
古川 守・杉田英昭 共著
蒸気タービン及び付属装置の構造、運転、保守、開放及び検査等について詳細に解説。LNG船用蒸気タービンプラントの章と演習問題を追加した改訂版。
【3訂版発行に当たって】
本書が1984年(昭和59年)に発行されて今年で35年, 2訂版が2009年(平成21年)に発行されてからも10年になります。最初に本書改訂版が発行された2002年(平成14年)は,舶用蒸気タービンがLNG タンクから漏れ出すボイル・オフ・ガスBOGを有効活用でき,またそれを有効に処理できる最も適した主機関として,LNG船に独占的に採用されていた時代でした。
……
海に由来する英語事典
ピーター D.ジーンズ 著/飯島幸人・丹羽隆子 共訳
英語の文書を翻訳する際に困ったことはありませんか?
イギリスと日本はともに海に囲まれた島国ですが、中国の古い文献に多大な影響を受けた日本語には、海や船員の言葉を語源とする用語はほとんどありません。しかし、かつて七つの海を制覇したイギリスの用語には、船内で使われていた言葉が多く日常語として使われています。一例を挙げると“Sling your hook”(錨を吊って出港)が「こっそりと逃げ出す」となり、新聞記事では「内閣からでていくべき」という意味で使われたこともあるといいます。
多くの民族の大移動が起こり、交流が盛んに行われてきた……
四・五・六級 航海読本(2訂版)
及川 実 著
過去に出題された海技国家試験を徹底分析。出題傾向に沿って重点解説。法令改正に伴い、内容を改めた改訂版。
【まえがき】より
船舶職員(船長や航海士など)を志す方々にとって,海技士の免許の取得は必須であり,そのためには海技士国家試験(以下「海技試験」という。)に合格しなければなりません。
海技試験の勉強をするうえで先ず把握しておかなければならないのが,学科試験の試験科目と試験の出題範囲です。海技士(航海)の資格における試験科目には「航海に関する科目」,「運用に関する科目」,「法規に関する科目」及び「英語に関する科目(六級海技士……
国際物流のクレーム実務−NVOCCはいかに対処するか―
佐藤達朗 著
クレームへの対応力の差がNVOCCの良否を決める!よくある事柄から共同海損、特殊ケースまでを実務的に解説。関係条約・規則も収録。
【はじめに】より
2007年7月27日にコンテナ船“WAN HAI 307号”とバルクキャリアー“ALPHA ACTION”号の衝突事件が発生した。その後、“WAN HAN 307号”の船主が共同海損を宣言し、共同海損として処理することとなった。
このような大きな共同海損事件は、年に何度となく発生するような種類の事件ではなく、2〜3年に一度発生するようなものである。したがって、日本国内……
商船設計の基礎知識【改訂版】
造船テキスト研究会 著
基本用語から法規にいたる概要、基本計画、船殻・船体艤装設計について、設計の実務者がわかりやすくまとめた入門書。
【まえがき】より
本書は昭和59年9月に初版を出版し、また平成7年に改訂した「商船設計の概要」の全面改訂版である。改訂に当たっては、新しい技術の進歩や関連する規則を取り入れて見直しを行ったほか、一層分かりやすい記述や各編の整合性にも充分な配慮を心掛けた。また書名もこの機会に「商船設計の基礎知識」に改めることにした。
本書の意図するところは、これから商船の設計を勉強しようと思っておられる学生や技術者に、実……
最新 水先法及び関係法令
国土交通省海事局海技課 監修
水先法と同施行令、同施行規則、同事務取扱要領及び関係法令を収録。(平成21年1月末日現在)巻末に標準水先約款、水先人試験の手引等併載。
<主な収録法令>
・全国水先区一覧
・水先法
・日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律
・水先法施行令
・水先法施行規則
・登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令
・海上物流の基盤強化のための……
四・五・六級 海事法規読本 3訂版
及川 実 著
過去に出題された海技国家試験を徹底分析。出題傾向に沿って重点解説。法令改正に伴い、内容を改めた改訂版。
【3訂版によせて】
本書は,海技士国家試験(海技試験)の試験科目の一つである,「法規に関する科目」について,主に四級,五級及び六級海技士(航海)を目指す方々を対象として「学科試験科目の細目」に合わせて関係法令の要点を整理・編集し,全てをこの一冊に網羅しております。
2訂版の発行以降,関係法令においては種々の改正がありましたが,その中で特に海上交通安全法及び港則法では,台風等の異常気象等に伴う船舶事故の未然防止策の充実・強化……