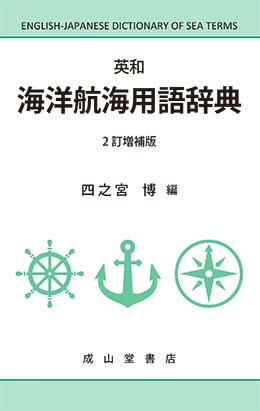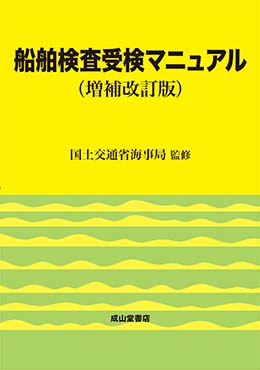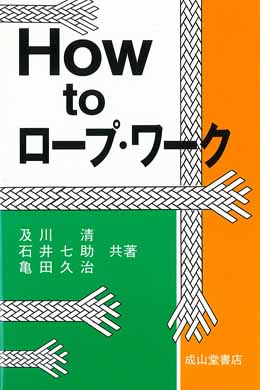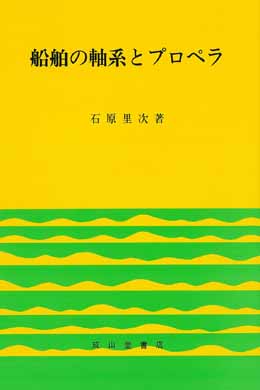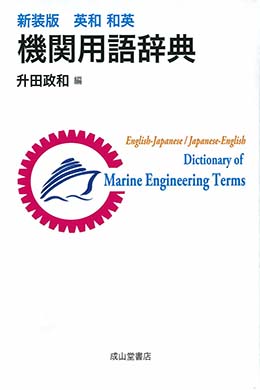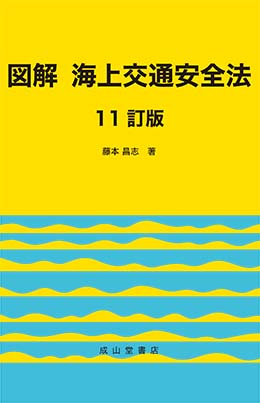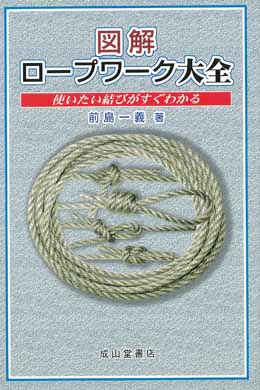海事の書籍紹介
英和 海洋航海用語辞典(2訂増補版)
四之宮 博 編
海技試験に持ち込めるハンディな海事英和辞典。
現場でも使えるロングセラーの改訂増補版。
収録していた14,000後に、ECDISなどの新しい航海計器や、無人運航船、バラスト水管理条約など、最新の環境規制・規則の関連用語を追加。
船の構造・設備・航海・運用、海洋、気象、漁業、海運、造船などの用語をすべて収録。
【まえがき】より
この本は、Sea TermsとはNatutical Termsといわれる用語の英和辞典として、当初10年の歳月を費やして編集されました。その内容は、船の構造・設備・運用・航海、海洋、気象、漁船漁……
船舶検査受検マニュアル(増補改訂版)【復刊】
国土交通省海事局 監修
「船舶検査の方法」に準拠して受検の方法を詳細に解説した、船主・造船所・メーカー等関係者必携の実務書です。また、整備記録・成績表など各種様式を豊富に掲載しており、すぐに役立つ内容。
【主な改訂のポイント】
・海水バラストタンク及びバルクキャリヤの二重船側部の防食塗装に関する検査の方法を追加。
・確率論による損傷時の復原性の検査の方法を追加。
・救命整備、圧力試験、電気艤装、BNWAS(航海当直警報装置)、VDR(航海情報記録装置)等の検査に関する
記述を追加、改正。
【はしがき】より
本書は、船舶安全法に基づく船……
六訂版 航海学 【上巻】
辻 稔・航海学研究会 共著
水路図誌、航程線航法、大圏航法、潮汐潮流などの地文航法とGPS、レーダなどの電波航法を解説。計算器を使った例題付。海技士(航海)1〜3級向。
【はしがき】より
航海学の専門図書としては多数の名著が出版されていますが、学生の能力に応じた適当な教材または参考書の発刊を望む声も少なくありません。
このような要望にこたえて本書が発刊されて以来20数年の年月が過ぎました。
この間、航海学の分野においても科学技術の進歩に伴い、各種電波計器の自動化、船位表示のデジタル化、自動衝突予防装置の開発、NNSS、GPSの普及等目覚ましいものがあ……
How to ロープ・ワーク
及川 清・石井七助・亀田久治 共著
基本的なロープの結び方、これを応用した各種の実用的な結び方・装飾的な結び方をイラストを中心にやさしく解説。万人向きの結びの本。
【まえがき】より
わたくしの家業の関係からか、小学生のころからロープを手にするようになったが、当時は、“よぼい”や“さつま”と読んでいた“垣根結び”や“ショート・スプライス”、あるいは“もやいむすび”などができる程度であった。
ところが戦時中の中学校の動員先が航空機の格納庫用天幕や爆弾用の落下さんの製作工場であったため、ここでもロープ・ワークやキャンバス・ワークをいや応なしに体得させられた。そして、……
船舶の軸系とプロペラ
石原里次 著
推進軸系とプロペラの保守・管理の実際を豊富な図面をもとに実務者、海技試験受験者向に解説。新しい推進技術も紹介する。
【まえがき】より
長年、練習船の機関士として、また、海難審判庁の審判官、理事官としての職務についてまいりました。この間に多くの先輩から貴重な指導を受け、また、実務にあたり、必要に応じていろいろな資料、参考書を集めてきました。今回、退職したのに伴い、これらの資料をこのまま散逸するのも惜しいとの思いから系統的に整理し、軸系装置についてまとめてみました。
モーターボートから大型船までの装置を対象にし、現在では実用……
英和・和英 機関用語辞典
升田政和 編
内燃機関の基本的用語を主に、―般船内用語、造船用語を厳選。教科書、参考書、海技試験に使われる学術用語を発音カナ付で収録。
【まえがき】より
本書は先に内燃機関を主とした「舶用機関用語集」として、各種の専門書から基本的な用語を採録し、一般船内用語、造船用語等を加えて、内燃機関の勉強の一助ともなるようにと公にしたものです。幸いにも各位のご支援によって版を重ねさせて頂きましたことを深く感謝いたしております。
しかし、初期の目的が内燃機関の基本的用語の勉学にあったために語数も少なく、また補助ボイラや遠隔装置、自動化の発達、それに……
図解 海上交通安全法 【11訂版】
藤本昌志 著
カラー図解で一目瞭然。航海の常識を完全理解!海には船舶の衝突を防ぐため「海上衝突予防法」「海上交通安全法」「港則法」(海上交通三法)が定められています。「海上交通安全法」は、船舶交通がとくに輻輳する東京湾、伊勢湾、瀬戸内海において、特別な交通方法を定めた法律です。
本書の特徴
■海上交通安全法を分かりやすい
カラー図解で条文ごとに解説
■航路や航法など必要な情報を図示
初学者の方はもちろん、改めて学習し直したい方にもおすすめです。
【まえがき】
船舶交通のふくそうする東京湾,伊勢湾及び瀬戸内海における船舶交通……
五訂版 航海学 【下巻】
辻 稔 著
天文概説から船位の決定に至る天文航法のすべてを理論と実際面から体系的に解説。海技試験問題例も多数収録しテキストに最適。1〜3級向。
【五訂版発行にあたって】
近年の航海学の進歩はめまぐるしく、天文航海学の分野においても同様です。かつて、天測による船位の算出は航海士にとって必携の技術でしたが、GPS等の普及により実務では六分儀を持つ機会も少なくなってきています。しかし、海技士を目指す人たちにとってその学習は必要不可欠なものであり、避けて通ることはできません。今回の改訂では、例題に卓上計算機での計算方法を具体的に示しました。また……
図解 ロープワーク大全−使いたい結びがすぐわかる−
前島一義 著
普段、特に意識されることは少ないですが、「結び」が必要な場面は意外と多いものです。日常生活においても古新聞・雑誌を束ねたり、靴ひもを結んだり、ダンボール箱にひもをかけたりと、枚挙に暇がありません。しかし、結び方が自己流であったり、状況に適した結びでなかったりなどして、緩んでしまったり、二度と解くことができなくなってしまうことも多くあります。
本書は基礎的なものから応用に至る約350通りの結び方を「この場面に適している結びは何か」がすぐわかるよう、用途別に分類しています。家庭で便利な結び方から、アウトドア、釣り、装飾、緊急時に使え……
金属材料の腐食と防食の基礎
世利修美 著
金属の腐食解明と防食対策に取り組む際に必要な概念や用語等の基礎知識を数式もまじえて、丁寧にわかりやすく解説した入門書。
【序文】より
本書は「腐食はどうもわからん!」と思っている方のために書かれた本である。特に、材料学や化学が得意でない技術者のために書かれたものである。
著者自身、企業の技術者として腐食防食の問題に直面し、困って独学した経験がある。アノードとカソード、陽極と陰極、正極と負極、電位と電極電位・・・等の専門用語に悩まされ、『電位の低い電極から高い電極へ腐食電流は流れる』と言った記述に「逆ではないのか?」と混乱した経験……