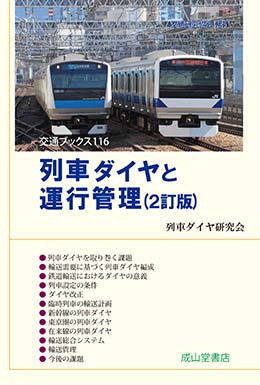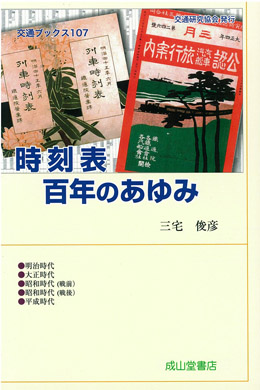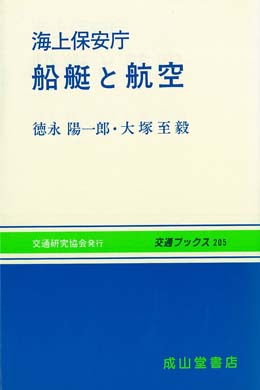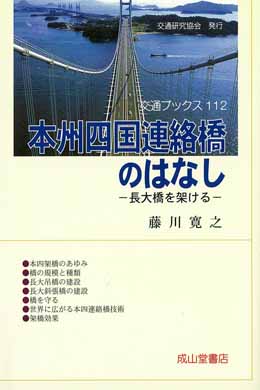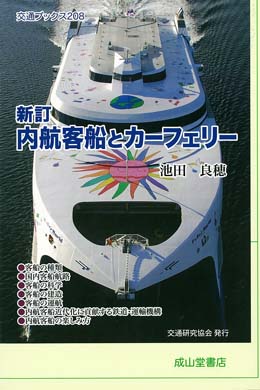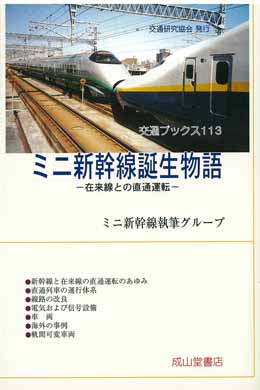交通の書籍紹介
列車ダイヤと運行管理(2訂版) 交通ブックス116
列車ダイヤ研究会 編著
鉄道会社の輸送のプロの教科書にもなり得るとともに、「鉄道」に興味をお持ちの方々の入門書としても最適です!
部門の連携を図り、鉄道運行を支える列車ダイヤ。ダイヤ作成には、需要予測、列車計画の諸条件や仕組みなどへの理解が必要です。日々の運行のためにダイヤはどのように構築されているのか?ダイヤ作りと運行管理の実際がわかる1冊です。
◆以下の情報を盛り込んだ2訂版!◆
・上野東京ライン、北陸新幹線、北海道新幹線開業のダイヤ改正まで対応した2訂版
・執筆はJR東日本運輸車両部所属の方たち
・列車を自国と位置で表し、安全・正確な輸送……
特殊鉄道とロープウェイ 交通ブックス105
生方良雄 著
ケーブルカー、モノレール、新交通システムやロープウェイ、トロリーバス等特殊鉄道の構造や歴史を説明。
第一章 鋼索鉄道(ケーブルカー)
鋼索鉄道の起源
戦時中の企業整備による休廃止
戦後の復活と新設
ケーブルカーの名前
四両が行き来するつるべ式もある
サンフランシスコのケーブルカーは循環式
ケーブルカーの線路の長さはケーブルの長さで決まる
ケーブルカーのポイントと軌間
安全なブレーキ
車両のはなし
巻揚所
幹線鉄道の循環式ケーブル・サンパウロ鉄道
懸垂式ケーブルカー
鉄道では……
時刻表百年のあゆみ 交通ブックス107
三宅俊彦 著
わが国の鉄道営業史を表している日本の時刻表の今昔を、時代背景の移りかわりと共に興味深く語った本。
【まえがきより】
わが国における月刊時刻表の刊行の歴史は100余年を有するわけだが、「時刻表」は各時代の鉄道の時刻のんみではなく、その時代の社会情勢や経済状態を示す貴重な史料の一つである。すなわち「時刻表」は「旅行用品」のカタログとして、明治・大正・昭和・平成4代の歴史の一断面を今日まで伝えている一次史料としての価値を有しているように思う。たとえば各年代の上野−札幌間の所要時間、東京−大阪間の運賃、箱根の旅館の宿泊料金などなど……
やさしい鉄道の法規−JRと私鉄の実例− 交通ブックス108
和久田康雄 著
鉄道の建設・運営・運賃・車両や施設・利用者との関係等に関連する鉄道事業法や鉄道営業法、その他各種法規をやさしく説明。
【はじめに】より
これまで「鉄道法規」の本は、極端にいえば鉄道会社の人が仕事の必要に迫られて読むぐらいだったのではないかと思う。しかし、この本は鉄道に関心のある方ならどなたでも分かっていただけるように、できるだけやさしく書いたつもりである。そのため、もともとの法律には規定があっても、実際にそれが働くことのないような条文(例えば個人営業の鉄道についての規定)や内部の手続きだけのことなどは、説明を省いてある。もっ……
新幹線−高速大量輸送のしくみ− 交通ブックス109
海上保安庁 船艇と航空 交通ブックス205
徳永陽一郎・大塚至毅 共著
白い精悍な船影にファンも多い世界屈指のコースト・ガード海上保安庁船艇のすべて。
同庁の航空業務の歩みと役割も紹介。
【目次】
第一部 船艇
第一章 海上保安庁船艇の任務と活動
1 海上保安庁創設の経緯
2 海上保安庁船艇の任務
3 海上保安庁船艇の活動
第二章 海上保安庁船艇の構成
第三章 海上保安庁船艇建造の歴史
1 創設期の船艇建造
2 更新充実期の船艇建造
3 新海洋秩序時代以降の船艇建造
第四章 海上保安庁船艇性能・装備の特色
1 復原性能
2 船体強度
3 耐航性
4 速力性能
5 居住性……
本州四国連絡橋のはなし−長大橋を架ける− 交通ブックス112
藤川寛之
行き来しやすくなった本州四国連絡橋。その建設の裏舞台を覗いてみませんか?世界最長の吊橋「明石海峡大橋」等、壮大なスケールの本四連絡橋を実現させた、世界に誇る日本の最先端技術を詳しく紹介。
【まえがき】より
本四架橋ができる前には、四国の住民にとって「四国が離島である」と実感するときが再々あった。それは、霧や風で船が出航できず毎朝配達されるはずの新聞が届けられないとき、本州に行く際に大きな荷物を持って長い桟橋を渡って連絡橋に乗り換えるときなどであったと思う。
多くの犠牲者を出した紫雲丸の悲惨な事故が契機となって、「早く架橋を実現して……
内航客船とカーフェリー(新訂) 交通ブックス208
池田良穂 著
環境の変化に翻弄されつつも、日々の努力と技術発展によって、業界激動の10年を乗り越えてきたその成果と現状を紹介する。
【新訂版発行にあたって】
本書初版を出して10年が経過した。内容を見なおしてみると、驚くほど内航客船の世界は変わっていた。特に、瀬戸内海にかかった3本の橋は、多くの内航客船航路を廃止に追い込んで、内航客船の数は激減していた。しかし、そうした中でも、巨費を投じた巨大国家プロジェクトとして完成した橋に果敢に挑むフェリーがあるのには感動を覚えた。
また、2泊以上の長距離航路では、飛行機との激しい競争によって船の数が……
ミニ新幹線誕生物語 交通ブックス113
ミニ新幹線執筆グループ 著
山形及び秋田から東京までを結ぶミニ新幹線誕生の物語。在来線との直通運転や厳しい自然条件等の試練を乗り越えた技術者達の挑戦記。
【発刊に寄せて】より
80年代後半に入って、整備新幹線計画から外れた山形県では、既存のインフラを活用して、高速鉄道ネットワークに乗り入れようとの機運が盛り上がり、JR東日本とともに新幹線と在来線の直通事業を推進した。この結果、狭軌の在来線を標準軌に改築して、専用車両による直通運転を行うようになった。このようにして生まれた山形新幹線をはじめとする「ミニ新幹線」は、地方の発想で作られたものといえよう。画一……
日本の港の歴史−その現実と課題− 交通ブックス212
小林照夫 著
港の誕生から現在迄を日本経済との関わりを中心に解説、エコポートの創造や成熟社会の下での経済機能面の強化など今後の課題にもふれる
【はじめに】より
日本は四方海に囲まれている。そのため、早くから海運が発達した。しかし、日本の港が本格的な外国貿易に携わるのは、横浜村に波止場が建設され、英・米をはじめとした欧米列強諸国との交易がはじまってからである。その意味では、わが国を代表する港、横浜といえど、ヨーロッパの港に比べると、その歴史は浅く、140年ほどに過ぎない。
開港当初、江戸時代の長い鎖国体制の下に置かれていたわれわれ日本人は、外国との……