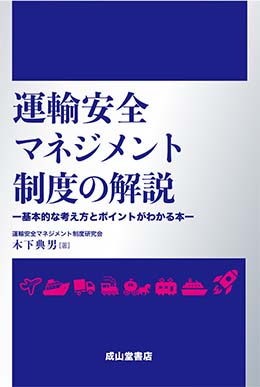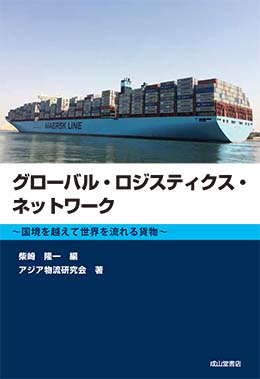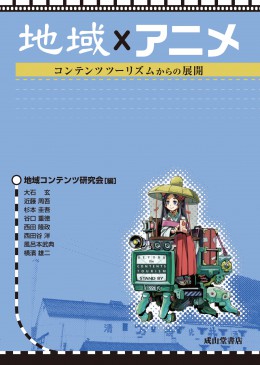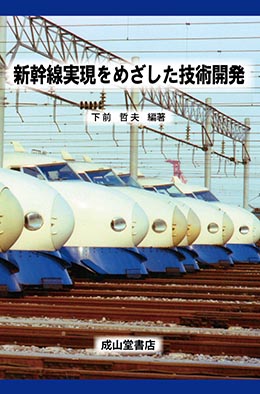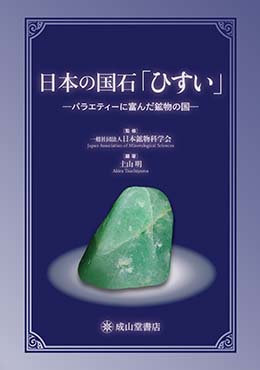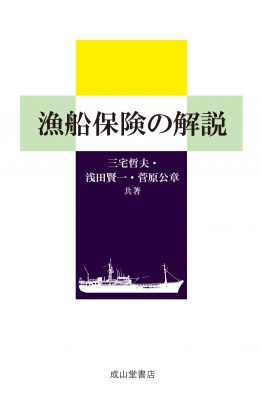成山堂書店の書籍紹介
台湾訪日旅行者と旅行産業ーインバウンド拡大のためのプロモーションー
鈴木尊喜 著
東京オリンピックを前に、日本は「観光立国」を掲げて海外からの観光客4,000万を目標とした政策を進め、訪日旅行者に対しても、政府、自治体、業者などがさまざまなアプローチをかけている。こうした状況のなか、近隣かつ親日国とされる台湾の訪日旅行者は、ここ数年爆発的に伸びてきている。本書は、台湾の訪日旅行産業を今日まで発展させた背景にある、日台関係の歴史や台湾の旅行業の制度や仕組み、歴史を解説するとともに、近年の旅行形態の変化を考察するもの。旅行事情や制度、歴史的背景を分析し、台湾訪日旅行産業を理解することで、日本側インバウンド事業者が、これ……
交通政治学序説
澤 喜司郎 著
政治と行政によって管理・統制されている交通に内在する疑問や問題を、法律、政令、省令を通して抽出し、同時に法治国家の法の限界を探ろうとするもので、交通政治学という新しい観点から交通にアプローチした内容です。
【まえがき】より
法治国家とは一般に、政治は法律に基づいて行われるべきという法治主義によって運営される国家、法により国家権力が行使される国家、国民の意志によって制定された法に基づいて国政の一切が行われる国家などとされています。しかし、法治国家では行政および司法が法律に適合していれば国民の権利や自由を侵害してもよいという形式的側面……
運輸安全マネジメント制度の解説ー基本的な考え方とポイントがわかる本ー
木下典男 著
「運輸安全マネジメント制度」が作られた契機は、平成17(2005)年に福知山線脱線事故を始めとする様々な運輸関係の事故が頻発し、「ヒューマンエラー」を要因とすると指摘されたことにあります。ここから、鉄道、自動車(トラック・バス・タクシー)、海運、航空の各運輸事業者自らが、経営トップから現場まで一丸となって安全管理体制を構築・改善し、国がその安全管理体制を評価する制度として始まりました。
本書は、「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律(平成18年法律第19号)」により、平成18(2006)年10月日から、陸・海……
グローバル・ロジスティクス・ネットワークー国境を越えて世界を流れる貨物ー
柴崎隆一 編/アジア物流研究会 著
国際物流の歴史、世界の海上輸送、世界各地における陸上貨物輸送などの現況から、中国が進める一帯一路構想や期待の高まる北極海航路といった現在的プロジェクトまで、世界の輸送ネットワークを俯瞰しながら国際物流の現状や実態、今後の動向をやさしく解説。
【発刊にあたって】
柴崎隆一先生を代表編者とした執筆陣が、地球スケールで広がる広域物流ネットワークの書籍を出版されました。海上輸送はもとより、ユーラシアや北米など大陸横断の陸上輸送の実態がつぶさに述べられています。とくにスエズ運河、パナマ運河、北米やシベリアの大陸横断鉄道などの歴史的展開か……
地域 × アニメ ーコンテンツツーリズムからの展開ー
大石玄/近藤周吾/杉本圭吾/谷口重徳/西田隆政/ 西田谷洋/風呂本武典/横濱雄二 共著
地方や特定の地域を題材にしたアニメが多く発表されるようになり、そのファンが現地を訪れ、物語を追体験する聖地巡礼やコンテンツツーリズムがブームとなっている。
こうしたことから現地を訪れるファンを取り込み観光地化する動きが全国で活発になっているが、一方で、こうしたファンや旅行者のニーズを必ずしも的確にとらえきれず一過性にものに終わってしまう、あるいは商業主義が全面に出過ぎてファンに見透かされてしまうといった例も多い。
そこで本書では迎え入れる側からの一方通行ではない、地域と旅行者、ファンのニーズをとらえ、どちらか一方からではない、両者が一……
新幹線実現をめざした技術開発
下前哲夫 著
世界初の高速鉄道である東海道新幹線。本書はそれを実現させた技術開発に焦点を当て、旧国鉄時代の記録や研究論文、専門誌の記事などを調査し、重要な役割を担った技術者たちの情熱や努力をたどったものである。コンピュータのない時代に実験装置を自作しながらも、世界に誇る高速鉄道技術を生み出した先人たちの発想や苦労を記した貴重な技術開発史である。
【まえがき】より
東海道新幹線は世界で初めての高速鉄道として、東京オリンピックが行われた1964(昭和39)年に開業しすでに50余年経ちました。
鉄道の新線建設はいつの時代でも大事業ですが、殊に東……
国鉄乗車券図録
池田和政 編
鉄道ファン、しかも国鉄時代のファンという方にオススメの1冊。
切符をつくるのに、元となった原図を収録。
これがないと、切符をつくることはできないんです。
約10年かけて、当時の膨大な資料を年代別に編纂した、類書なき1冊。
[caption id="attachment_7427" align="aligncenter" width="212"] このように本文で紹介しています[/caption]
【はじめに】より
国鉄で使用された乗車券は、明治5年6月12日、品川―横浜間仮営業時から使用され、その乗車券は国内で印刷……
航海訓練所シリーズ 読んでわかる機関基礎(2訂版)
独立行政法人 海技教育機構 編著
三級・四級海技士の習得に必要な力学、工学、電気などの理工系分野の知識を、現役の機関士が実務経験を踏まえて、初学者向けに解説。
【はしがき】
船舶には、主機関、蒸気ボイラ、発電機、空気清浄機、冷凍装置、空調装置、電気設備、ポンプ、各種の弁、甲板機器等様々な種類の機器が搭載されている。船舶機関士は、これらの機器を正しく運転操作することはもちろん、それぞれが持つ特性を最大限に発揮させるため、日々の運転監視や計画的な解放整備・調整の業務を行っている。
これらのためには、船舶機関士は各機器の構造作動、 運転操作の取り扱い並び来歴に関し……
日本の国石「ひすい」ーバラエティに富んだ鉱物の国ー
一般社団法人 日本鉱物科学会 監修/土山 明 編著
(一社)日本鉱物科学会が2016年9月実施した「日本の国石」選定事業を導入部として、「石」の定義から「石」を調べて地球の歴史を探り宇宙とをつなぐ学問である「鉱物学」について、そして「国石」に選ばれた「ひすい」と日本・日本人との古くからの関わりや多様な地形をもち多くの鉱物が産出される日本の地質的な特異さ、資源としての利用や石との身近な楽しみ方まで、アカデミックな基礎知識を盛り込みつつ、日本の「石」「岩石」「鉱物」の魅力を存分に伝える。
※クリックすると拡大します
【はしがき】
一般社団法人 日本鉱物科学……
漁船保険の解説
三宅哲夫・浅田賢一・菅原公章 共著
2017年に日本漁船保険組合が設立されました。また、2016年には漁船損害等補償法が改正され、漁船保険制度の大改革が行われました。本書は刷新された漁船保険制度の内容を全般的に解説しています。
【はしがき】
2017年(平29)4月1日、全国45の漁船保険組合と漁船保険中央会が統合一元化され日本漁船保険組合が設立されました。漁船保険は、1937年(昭12)の漁船保険法の制定によって発足し、戦後の1952年(昭27)に漁船損害補償法が制定され、その後、数次にわたって改正が行なわれてきました。日本漁船保険組合の設立は、漁船保険制度……