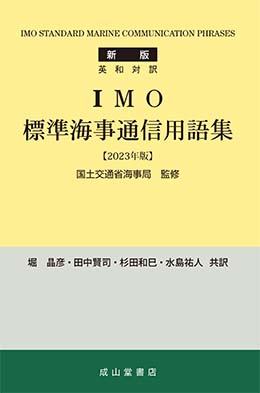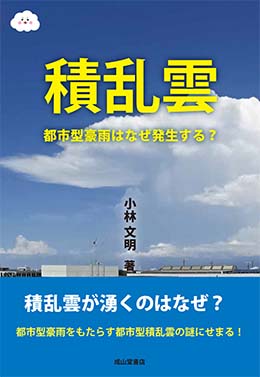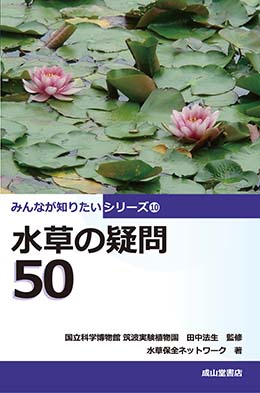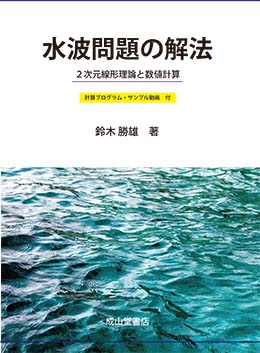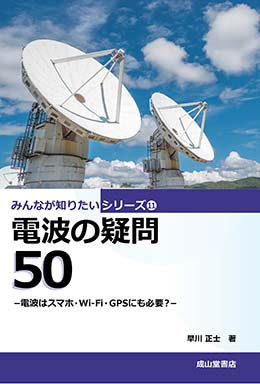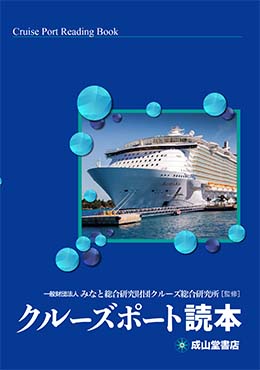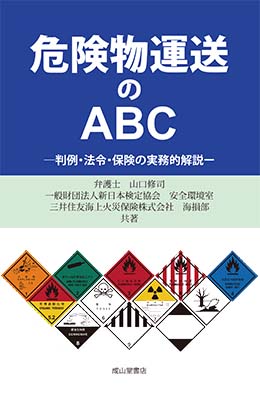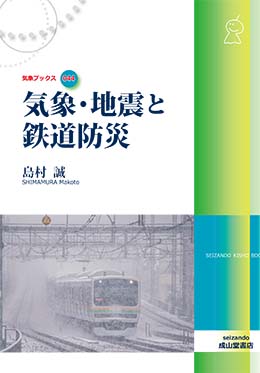成山堂書店の書籍紹介
新版 英和対訳 IMO標準海事通信用語集【2023年版】
国土交通省海事局 監修/堀 晶彦・田中賢司・杉田和巳・水島祐人 共訳
1995年に改正されたSTCW 条約(1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約)において,甲板部の職員に対し最低必要要件としてこれを理解し使用する能力が強制要件として求められている『IMO 標準海事通信用語集』が成山堂書店より対訳版で出版されたのは1999 年でした。
2002年にそのSMCPがさらに改訂され,その使用が現在の強制要件となっています。本翻訳は,その当時IMOのホームページよりダウンロードされたresolition XXXにより作成されたものです。付録として従来のものに加え,内容を少しでも確認……
積乱雲 ー都市型豪雨はなぜ発生する?ー
小林文明 著
大好きな積乱雲を観測し続けて30年の著者が解説する極端気象の第3弾!
雲の中でも激しい雷雨や雹を降らせる積乱雲は特殊です。あのモクモクの中ではどんなことが起こっているのでしょうか? 本書は、積乱雲の発生から内部構造、組織化といった積乱雲の特徴をまとめました。また、近年増加傾向にある豪雨災害について、具体的な事例をもとに豪雨のメカニズムから身の守り方までを解説します。
■小林先生が動画で紹介
●その1
●その2
●その3
【はじめに】
豪雨をもたらす積乱雲、竜巻をもたらす積乱雲、落雷をもたら……
水草の疑問50 みんなが知りたいシリーズ10
国立科学博物館 筑波実験植物園 田中法生 監修/水草保全ネットワーク 著
水草は、普通に「植物」と呼ばれて陸上に棲んでいるものが、水中で暮らせるように進化した植物と言われる。本書ではそのような水草の世界のさまざまな不思議、疑問を掘り起こし、それぞれを専門とする研究者が本シリーズの例にならって、一問一答式で回答している。その生態や進化はもちろんのこと、水草を衣食住に利用する文化、水槽で楽しむ趣味の世界まで、広く網羅した内容。
中身を見てみる
【はじめに】
水草は,水の中で生活しています。
水草なのだから当たり前のことだと思われるかもしれません。
それでは,もしも私たち霊長類の一種が水中で暮……
水波問題の解法 ー2次元線形理論と数値計算ー
鈴木勝雄 著
重力の作用によって、水面に生ずる重力波―水波。
この水波の中に、静止したり、揺れ動いたり、進行したりする物体があるときに、その物体の周りに波がどのように生じ、変形するのか。物体には、どのような力が働き、どのように揺れるのか。
コンピューターの発展により、純数値計算が容易になった現在、あらためて古典的な計算方法を用いた解法を学び、その意義を問い直す。
計算プログラム・サンプル動画 付
【計算プログラム・サンプル動画】は以下からダウンロードしてください。
【計算プログラム】
■低常造波問題
SemiSubCircle……
なるやま君マスキングテープ
なるやま君
なるやま君グッズ第2弾。
和紙で出来たマスキングテープです。
幅15mm、長さ10m。
マスキングテープはしっかりついて剥がれやすく、跡になりにくいからとっても便利。
いろんなところにペタペタ貼ることができるんです。
なるやま君の可愛らしい姿をあちこちに貼れますよ。
※お支払いはクレジットカードでお願いいたします。
電波の疑問50ー電波はスマホ、Wi-Fi、GPSにも必要?ー
早川正士 著
身近だけど意外と知らない電波の世界へようこと。
Q.電波はどのように利用されているの?
Q.電波ってなに?
Q.電波はどうやってつくるの?
Q.自然に出る電波ってなに?
Q.電波を感じる生物はいるの?
Q.Wi-Fiは電波なの?
Q.腕時計型ウェアラブル電話ってなに?
など、電波のことについて正しい理解をするための50の疑問に、電波環境学の専門家が丁寧に答えます。
中身を見てみる
【はじめに】
電波は目に見えないのですが,地上空間にたくさん行き交い,そしてさまざまなことに応用されています。ところ……
世界の空港事典
岩見宣治・唯野邦男・傍士清志 共著
地球上にあまねく広がる航空ネットワーク。 その拠点たる世界各国の209空港と、 日本の97空港を航空分野のプロフェッショナルが余すところなく解説。
世界中に網の目のように張り巡らされた航空ネットワークの拠点である「空港」について、これでもかと情報を盛り込み、解説した本邦初のオールカラー事典です。解説しているのは、空港計画、建設、維持運営に携わる現場のエキスパート。空港について語らせたらこれ以上いない執筆陣が、空港の成り立ち、特徴、諸問題から今後の拡張計画まであらゆる視点で説き起こしていきます。
本書は主に前後半の2部構成となっ……
クルーズポート読本
一般財団法人 みなと総合研究所クルーズ総合研究財団 監修
現在、クルーズ人口は増加の一途を辿っており、国は「2020年にクルーズ訪日旅客数500万人達成」を目標として掲げている。それを踏まえ2017年10月に実施された「クルーズポート・セミナー」の講演内容(海事関係団体、大学、官公庁や自治体など各界の識者6人が演者)を第1章のベースとして書き起こし、クルーズの歴史に始まり各港の取り組みや国内外の現状や課題までを概説している。それらを補完するものとして、2章以降に国交省港湾局の出したクルーズ船受け入れのための「ガイドライン」、クルーズポートに関する基礎知識を整理した「関係用語集」と「Q&A」、……
危険物運送のABCー判例・法令・保険の実務的解説ー
山口修司・一般財団法人 新日本検定協会 安全環境室・三井住友海上火災保険株式会社 海損部 共著
危険物とは何かから、商法改正が危険物運送にどのように影響するのかまで、法律・実務・保険の専門家がそれぞれの立場からわかりやすく解説。
【はしがき】より
平成30(2018)年5月18日、「商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律」が国会を通過し、成立しました。商法のうち、運送及び海商に関する部分は、六法で唯一文語体の法律として残っていましたが、今回の改正で、口語体の法律となりました。
商法の運送及び海商の部分は、明治32(1899)年の制定以来改正もなされず100年以上が経過しています。
平成26(2014)年2月……
気象・地震と鉄道防災 気象ブックス044
島村 誠 著
日本は明治の初めに欧米から鉄道技術を取り入れたが、国土が狭く、厳しい自然条件の日本に鉄道を敷設するにはさまざまな制約があった。建設技術が未熟な時代につくられた線路・トンネル・鉄橋をいかしながら、少しでも安全性と利便性を高めるよう努力してきた鉄道会社の営みを、鉄道技術者の立場からまとめた内容。
【はじめに】
日本の鉄道技術は、自然条件が大きく異なる欧米から明治の初めに直輸入されて以来、南北に細長く急峻な地形のため様々な自然災害が頻繁に発生する国土のきびしい環境条件に適応する努力を絶え間なく続けながら発達してきた。
たと……