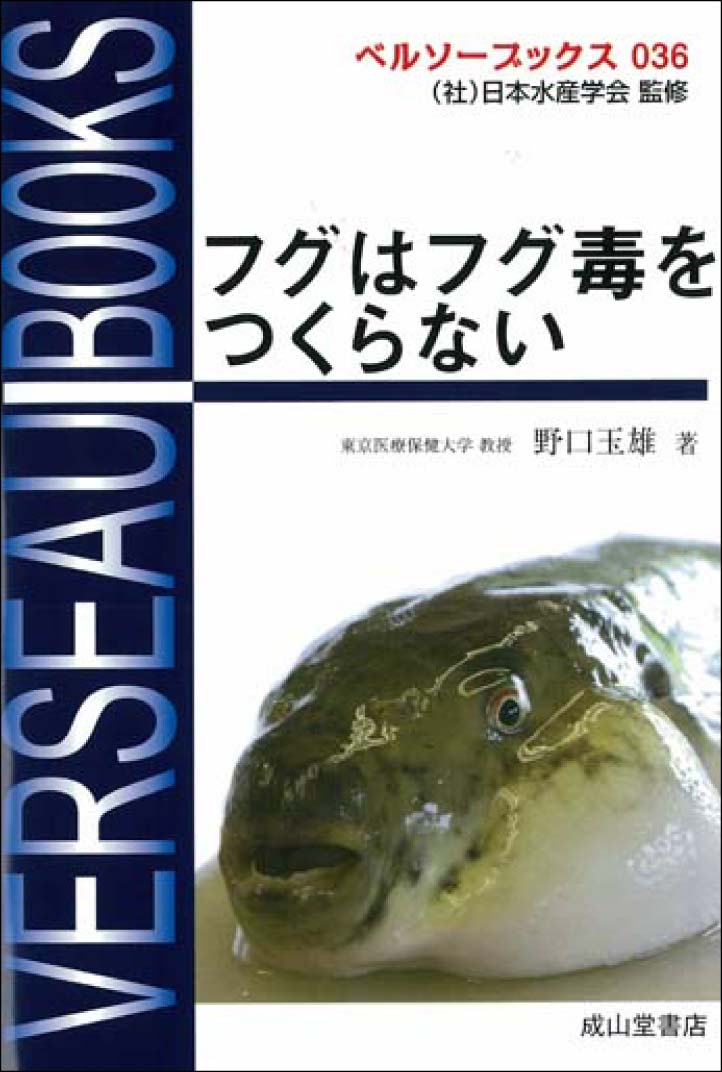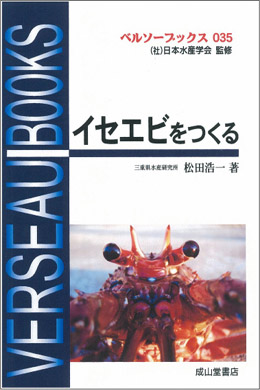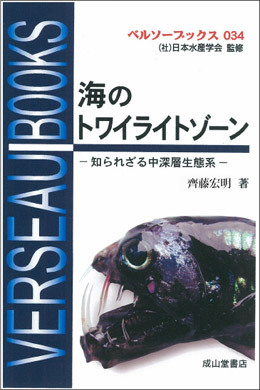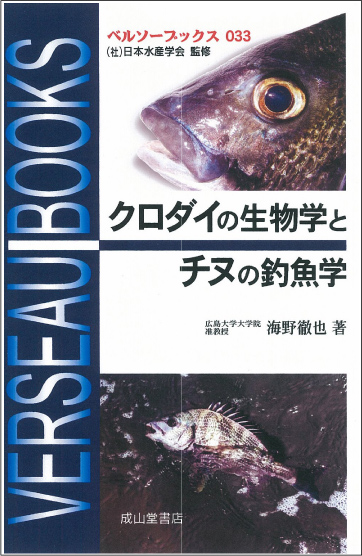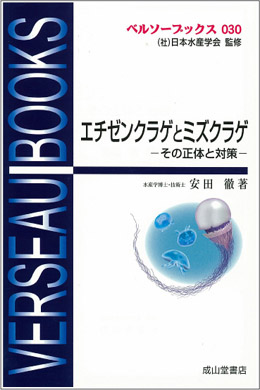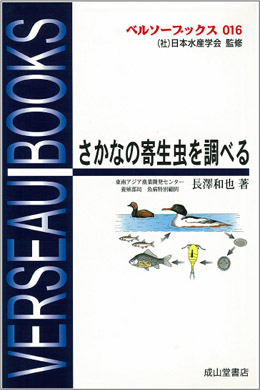水産の書籍紹介
フグはフグ毒をつくらない ベルソーブックス036
野口 玉雄 著
陸上養殖のトラフグは無毒になり、海にも陸にもフグ毒をもつ生き物がいることがわかった!
フグはなぜフグ毒をもつのか、またもち得るのか?フグ毒研究とフグ利用法の最新の成果がここに。
【はじめに】より
フグは昔から日本人に親しまれ、愛されてきた魚である。身に危険が迫ると大きく膨れ上がる、そのユーモラスな姿が私たちの心を捉えているのだろう。しかし、愛嬌だけがフグの人気の源ではない。フグは当たれば死んでしまうことから「鉄砲」と呼ぶこともある。しかし、白身魚の王と言ってもよいほど美味しい。手を出したくとも高価で容易には出せないことも人気……
魚との知恵比べ−魚の感覚と行動の科学−【3訂版】 ベルソーブックス004
川村軍蔵 著
もっと魚を釣るために、もっともっと釣りを楽しむために、魚のことを知りつくした研究者が書いた本をオススメします。魚は色がわかるのか?魚は1度釣られると学習するのか?釣り糸は見えているのか?初心者からベテランまで、マニュアル本には載っていない釣りのヒントが満載。
【はじめに】より
魚の行動に興味をもつ動機は人によって様々で、自分が飼っている熱帯魚に自分の意志を伝えたいためにその魚を知りたいという人もいれば、もっと釣りが上手になりたいために魚の行動を知りたいという釣り愛好家もいるだろう。最近は、自然環境保全という考えが浸透し、希少魚……
イセエビをつくる ベルソーブックス035
松田浩一 著
生まれた時のクモのような姿からガラス細工のように繊細な稚エビとなり、最後は威風堂々とした姿に成長するイセエビ。初めて幼生の人工飼育に成功した著者がその不思議な生物を、最新の研究成果とともに紹介する。
【はじめに】より
イセエビ は磯の王者である。長年イセエビのことを研究し、思い入れが強い筆者であるのでかなり贔屓目に見ている感はいなめないが、確かにそう思う。磯に棲む生物としては魚類を除いて最大のものであり、体長35cm、重さ2kg以上にも成長する。このような大きさのイセエビは、もはや片手では持てずに、両手でしっかりとつかんでもやっと……
海のトワイライトゾーン−知られざる中深層生態系− ベルソーブックス034
齊藤宏明 著
水深150メートルを超えると太陽の光がわずかに届く薄暗い世界が広がっている。この世界に潜む生物たちはどのような生存競争を繰り広げているのだろうか? 最新科学のサーチライトを当ててみよう。
【はじめに】より
波間に太陽の光がきらめく暖かい海の表面から潜っていくと、次第に太陽の光が弱まり、薄暗くなってくる。やがて、水は冷たくなり、僅かに光を感じはするが、物の形は薄暗さの中にぼんやりとしか浮かび上がらなくなってくる。水深200mから1,000m程の深さの海には、このように僅かしか光が到達しないトワイライトゾーン(薄暮帯)と呼ばれる……
クロダイの生物学とチヌの釣魚学 ベルソーブックス033
海野徹也 著
クロダイには色が分かるのか?
釣り糸は見えているのか?
あなたは本当にクロダイのことが分かっていますか?
クロダイを“彼女”と呼ぶほどにチヌ釣りを愛し、クロダイの研究を探し続けてきた著者が最新の研究成果と釣りの経験を融合してまとめた待望の「チヌ学」入門書です。
【はじめに】より
魚の中で有名な魚といえばマダイやマグロかもしれない。これをタイの仲間に限定するとマダイであり、次はクロダイであろう。それにクロダイは知名度が高いだけでなく、水産業においても重宝されている。日本では“捕る漁業から作り育てる漁業”を合言葉に栽培漁業が……
海藻の食文化 ベルソーブックス014
今田節子 著
健康食として注目されている海藻。日本では古くから薬効をもつ食べ物として、今よりも多種類の海藻が利用されていた。
海藻の食文化を見直すことで、新しい利用法も見えてくる!
【目次】
第1章 海藻とは何か?海藻の食文化を理解するために?
1-1 海藻と海草はどう違う
(1)海藻と海草を区別する
(2)海草利用の伝統
1-2 海藻の分類と特徴
(1)色による海藻の分類
(2)「〜モ」「〜メ」「〜ノリ」
1-3 海藻が生える環境とその採り方
第2章 食用海藻の種類と移り変わり
2-1 食べている海藻は一握り
2-2 昔はた……
エチゼンクラゲとミズクラゲ−その正体と対策− ベルソーブックス030
安田 徹 著
ふぅわり、ゆらゆら
優雅に海中を漂う美しいクラゲたち。
心を癒すものもいれば、
人々に大きな被害を与えるものもいる。
不思議に満ちたクラゲたちの生態、被害対策、利用法を探る。
【はじめに】より
近年、温暖化に伴う地球環境(大気や海洋等)の変化・異常現象が話題となっています。新聞、雑誌やテレビなどのメディアを通じて、私たちは世界規模で起こっているその現状を知ることができます。海洋に関することでは、海面の水位や水温の上昇、豪雨による沿岸土砂の流入等がとりあげられ、今後の見通し・予測が論じられています。
では海洋生物ではどうでしょうか。最……
マグロは絶滅危惧種か ベルソーブックス015
魚住雄二 著
健康食として注目されている海藻。日本では古くから薬効をもつ食べ物として、今よりも多種類の海藻が利用されていた。
海藻の食文化を見直すことで、新しい利用法も見えてくる!
【目次】
第1章 海藻とは何か?海藻の食文化を理解するために?
1-1 海藻と海草はどう違う
(1)海藻と海草を区別する
(2)海草利用の伝統
1-2 海藻の分類と特徴
(1)色による海藻の分類
(2)「?モ」「?メ」「?ノリ」
1-3 海藻が生える環境とその採り方
第2章 食用海藻の種類と移り変わり
2-1 食べている海藻は一握り
2-2 昔はた……
海洋微生物と共生−サンゴ礁・海底熱水孔の生き物たち− ベルソーブックス031
石田祐三郎 著
葉緑体やミトコンドリアは別の生き物だった!きらめくサンゴ礁を支えているのは何か?光も酸素もない深海底に生物がひしめいていた!生命活動、進化、地球環境の維持から健康維持まで、驚異と不思議に満ちたミクロの共生の世界。
【はじめに】より
生き物は程度の差こそあれ、互いに助けあったり、潰しあったりして生きている。
本書に取り上げた海洋におけるサンゴと褐虫藻、海綿と微生物、ハオリ虫と最近等々は、大変興味深い「助け合い」の共生関係にある。ただ、主役である微生物が肉眼で見ることが難しいなど、一般の読者には馴染み難く、専門用語も読者の理解を得にくい……